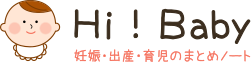私の娘は生後10ヶ月の時、卵黄や卵ボーロを経て、全卵デビューを果たしたと思ったら、全身蕁麻疹が発生し、顔・目・耳まで真っ赤に腫れ上がってしてしまいました!
生後10ヵ月まで何事もなく離乳食後期を迎えていたので、まさかアレルギーが出るとは思わず、完全に気を抜いていた時でした…。
ここでは、そんな私自身の経験をもとに、卵アレルギーの症状や、アレルギー発現時の病院受診について、治療や検査の経過についてまとめています。卵アレルギーに限らず、赤ちゃんのアレルギーが心配な方や今アレルギーが出てるけどどうしたらよいのか困っているお母さんの参考にしていただけらと思います。
赤ちゃんの食物アレルギーについて
赤ちゃんは消化・吸収機能が未熟ということもあり、特定の食べ物を『異物』と見なすことがあります。すると、その『異物』に対してアレルギー反応が起こってしまうのです。
症状は次の項目で詳しく説明しますが、最悪の場合、アナフィラキシーショックを起こし、気道閉塞による呼吸障害や、ショック(血圧が下がって命の危険もある)となる危険性もあるので、初めて食材をあげるときには、特に注意しなければいけないのです。
食物アレルギーの症状

アレルギー反応を起こした場合、外の皮膚が赤く腫れるよう、体の中の粘膜も赤く腫れます。
この腫れが喉頭(空気の通り道)や腸に強く現れたときには、呼吸の症状や、お腹の症状が現れることがあります。
皮膚に出る症状
- 蕁麻疹
(膨隆した赤い発疹がかたまってでる)

- 痒み
(不機嫌になる) - 紅潮・むくみ
(特に顔やまぶた、耳など)
呼吸の症状
- 喘鳴
(呼吸がゼイゼイ・ヒューヒューする) - 咳
- 鼻水
- 呼吸困難
(苦しそうにしている)
お腹の症状
- 嘔吐
- 下痢
- 腹痛
アナフィラキシー・アナフィラキシーショックの症状
アナフィラキシーは医学的には、「アレルゲン等の侵入により急速に発症した重度の全身性アレルギー反応で、死に至る危険があるもの」と定義されています。
簡単に言うと、短時間(数秒~数時間)のうちに皮膚・呼吸器・消化器など複数の臓器にアレルギー反応が現れた状態を言います。
例えば、蕁麻疹と呼吸困難がある場合や、喘鳴と嘔吐がある場合などです。
この他に、血圧低下や意識障害などの循環器障害が現れた場合は、『アナフィラキシーショック』と呼ばれます。
もしアナフィラキシーショックを起こすと、血液が心臓や脳に行き届いていない状態ということなので、命の危険を伴います。
食べてからアレルギー症状が出るまでの時間

アレルギーは、食べてすぐ現れるものだけではなく、ゆっくり現れるものもあり、主に3つのタイプに分かれます。
即時型
食物摂取の、15~30分後(2時間以内)に症状がでるタイプ。
この即時型が最も多く、アナフィラキシーなど重篤な症状がでるのも、この時間になります。
遅発型
食物摂取の、6~8時間後に症状がでるタイプ。
遅延型
食物摂取の、1~2日後に症状がでるタイプ。
私の娘は、14時に全卵を食べて17時頃から蕁麻疹が広がり始めました。ただ、15時ころからは不機嫌だったので、私が気が付けなかっただけで、即時型のアレルギーとして何かしらの症状は出ていたのだと思います。
私は、30分症状が出なければまず安心…と思って完全に油断していましたが、即時型であってもすぐに症状が出るとは限りません!
食後2時間は特に、赤ちゃんの様子や皮膚の状態を注意深く観察してあげましょう。
症状が出てから治まるまでの時間

アレルギーの症状は、食べ物が消化・吸収されるまで時間がかかるので、症状が出始めてから1~2時間は悪化することが多いです。
その後、数時間で症状が治まる人もいれば、1週間続く人もいますし、1度症状が治まっても数時間後に再びぶり返すこともあります。
病院を受診して、適切に治療をすれば、数時間~1日で症状は改善することが多いです。
アナフィラキシーショックなど重大なアレルギー反応を起こした場合でも、適切な治療ができれば1~2日で退院できることがほとんどです。
娘の場合は、19時頃に処方された薬を飲ませたところ、24時頃には、顔の紅潮や全身の蕁麻疹もほとんどなくなっていました。
翌朝、若干瞼が腫れているかな?と思いましたが、昼には症状は全くなくなっていました。
アレルギーを起こしやすい食品
第1位 卵

卵白に含まれる「オボムコイド」という成分が主にアレルギーの原因となります。
最もアレルギーを起こしやすい食品とされています。私のように、他の食品で全く症状がないからと言って油断しないほうがいいですね^^;
第2位 牛乳

牛乳や乳製品に含まれるたんぱく質がアレルギーの原因となります。
牛乳や乳製品のアレルゲンは、加熱や加工でも力が弱りにくい特徴があるので、調整乳やチーズなどの加工品にも注意しなければいけません!
第3位 小麦

パンやうどんなど多くの食品に含まれている小麦もアレルギーを起こしやすい食品です。
摂取量が少量ではアレルギー症状がなくても、摂取量が増えてくるとアレルギーが出ることもあるので、注意しましょう。
そば

蕎麦は、小麦につづいて4番目にアレルギーを起こしやすい食品ですが、少量でも激しいアレルギー症状を起こしやすい食品になります。
蕎麦アレルギーだと、そば殻枕やお蕎麦屋さんでそば粉を吸引することでもアレルギー反応を起こすこともあるので、蕎麦には近づかないことが賢明です。
えび

えびは、呼吸困難などひどいアレルギー反応が出る場合もあるので、早くても1才から、出来れば離乳食期は避けたい食品です。
かに

えびやかになどの甲殻類のアレルギーは同時に持っていることが多い食品です。
えびアレルギーにも言えることですが、食品に触れただけでも蕁麻疹や痒みなど皮膚症状が出ることがあります。
ナッツ

ピーナッツやクルミ、アーモンドなどのナッツ類はアナフィラキシーなど激しいアレルギー症状を起こしやすい食品です。
ナッツをそのまま食べなくても、お菓子や杏仁豆腐、カレールーなど加工食品に入ってることも多いので、原材料をチェックするようにしましょう!
ちなみに、赤ちゃんにナッツ類はあげられません!!早くても2~3歳からにしましょう。
その他
キウイ、オレンジ、大豆、豚肉、いか、鮭、鶏肉、牛肉、さば、りんご、バナナ、ももなど、離乳食であげる機会が多い食品もアレルギーを起こす危険性があります。
ただ、危険があるからと言って、完全にアレルゲンを除去してしまうと、逆に食材に敏感になって、アレルギーを起こしやすくなる(小児科医に聞いた話)ので、適切な時期に1さじずつ気をつけながら与えていきましょう。
病院受診のタイミング

呼吸やお腹の症状が出ている時
皮膚だけではなく、呼吸やお腹の症状が出ていたらアナフィラキシーと言って、重いアレルギー反応を起こしているので、すぐに病院を受診してください。
この時、赤ちゃんがちょっと元気がないレベルではなく、焦点も合わず様子がおかしい時や、呼吸がとっても苦しそうな時にはアナフィラキシーショックを起こしている可能性が高く、早急な医療処置が必要な状態です!すぐに救急車(119番)を呼びましょう!
ちなみに、アナフィラキシーショックは、血圧が低下しますが、皮膚症状などにより、顔色の変化がわかりずらいので気をつけましょう。
蕁麻疹などアレルギー症状が出たとき
蕁麻疹だけであれば遅くても数日で、自然と症状は改善してきます。
ただ、蕁麻疹から徐々に呼吸やお腹の症状が出て、アナフィラキシーを起こす時もあります。悪化させないためにも、アレルギーを疑ったら病院受診するようにしましょう!
薬でしっかり治療することで、アレルギー症状も比較的すぐ改善されて、赤ちゃんにとってつらい症状を消してあげることができます。
また、アレルギーを起こした食材について、必要によっては検査を受けて、医師の指導のもと正しい対処をすることが、赤ちゃんの健康を守ることにつながります。アレルギー反応が局所的な場合も、遅かれ早かれ病院は受診するようにしましょう。
アレルギーに使う薬について

アナフィラキシーを含めアレルギーが出た場合、抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬、そしてステロイドが使われます。
- 抗ヒスタミン薬
アレルギー反応を起こすヒスタミンの作用を抑えてアレルギー症状を素早く抑えます。ただ、副作用として眠気をおこしたり、乳児では痙攣を起こした例もあるとのことでうす。そのため、小児科では抗ヒスタミン薬より、下の抗アレルギー薬が処方されることが多くなっているようです。 - 抗アレルギー薬
アレルギー反応を起こすヒスタミンがの発生を抑える薬です。効果としては、アレルギーの発症予防で、今出ている症状を鎮めることはできません。 - 第二世代抗ヒスタミン薬
この薬は、抗ヒスタミン薬と抗アレルギー薬の特徴を持った薬で、アレルギーの発症と症状を鎮める効果があります。
これは、乳児でも使える薬があり、10ヶ月の娘にはエピナスチン塩酸塩という薬が処方されました - ステロイド
アトピー性皮膚炎の治療薬にも使うように、アレルギー症状を抑える効果があります。
娘には、リンデロンシロップが処方されました。
この他に、アナフィラキシーを起こしている場合には、アドレナリン注射や点滴で治療が行われます。
- アドレナリン(ボスピン/エピペン)
血圧低下や呼吸困難、強い腹部症状がある重症例で使われます。
速効性がありますが、一度の注射では効果が得られない場合もあるので、数回使用することもあります。
卵アレルギーの検査
血液検査(抗体測定)
大人と同じように採血をして、各アレルゲンに対してのIgE抗体の量(抗体価)を測定します。
IgE抗体は、特定のアレルゲンが侵入してきたときに、アレルギー反応を起こす物質で、200種類以上のアレルゲンに対するIgE抗体を測定することができます。

この数値は、低ければアレルギー症状が出にくく、高ければ高いほどアレルギー症状が出やすいことを示します。
娘も、卵の他に、まだ食べたことのないえび・かに・ナッツや、ねこ・いぬなど一緒に検査してもらいました。
ちなみに、乳児は、消化機能が未熟ということに加え、このIgE抗体を作りやすいため、大人よりも食物アレルギーを起こしやすいそうです。
皮膚検査(プリックテスト)
アレルゲンとなる食品の成分を皮膚に付け、その上から皮膚に血が出ない程度に軽く傷をつけて、反応をみる検査です。
15分後に、傷をつけた部位にできた膨疹の大きさを図り、アレルギーの有無を判定します。
まとめと反省

食物アレルギーは、10人中1人の乳児に起こると言われています。
私は、アトピー持ちで娘も乳児湿疹がひどく出ていたのにも関わらず、正直『そうは言っても大丈夫だろう…』と油断していました。
この時もしかしたら、アナフィラキシーなど命にかかわるような状況になっていた可能性も否めません…。
私が、今回の反省を踏まえて、学んだことを下にまとめてみました。
何ヶ月になっても初めて食べるものは、1さじのみ!
10ヶ月になり、卵黄・卵ボーロもクリアしていたので、全卵も大丈夫だと思い、1さじ用意する手間を惜しんでしまいました…
初めての食材は1才を過ぎてからも1さじずつあげるようにしましょう。
初めての食材は、平日の午前!
私は、普段1時ころに昼食をあげるのですが、娘のお昼寝が長引いたこともあり、その日の昼食は2時になってしまいました。
そして症状に気が付いたのが17時だったので、近くの病院は受付が終了していて、病院探しも一苦労でした…。
アレルギーがでた場合に、すぐに受診ができる平日の午前中に与えるようにしましょう。
食べた後2時間は、症状に要注意
即時型のアレルギーでも、摂取して2時間後に症状が現れることがあります。
娘のように、不機嫌になっているときにはアレルギーの徴候かもしれません。赤ちゃんの様子や呼吸・皮膚・お腹の症状を注意深く観察してあげてください。